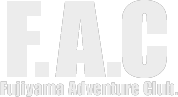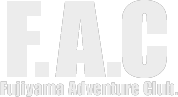ラフトボートのご紹介
FACでラフティングのツアーに使っているゴムボートのご紹介です。
通常はラフトと呼びますが。コレはイカダとゆう意味でラフティング発祥の地
アメリカでの呼び方をそのまま使っているものです。
発祥はアラスカの金鉱堀が使った丸太船(イカダ)にあると言われています。
川下りを楽しむこのゴムボート。
FACでは複数のメーカーのモノを使用しています。
主にはゼベック(韓国製)、インセプト(ニュジーランド)アーク(南ア)などです。
当社では3社を使用してますがその他にも多数のメーカーがあり特色があります。
モチロン、国産メーカーもあり。アキレス、ライケンなどが有名です。
材質もゴム系、軟質塩ビとあり。特色があります。
FACのボートですとゼベック、アーク(軟質塩ビ)、インセプト(ゴム系)でボートの性能や性質に
違いがありガイドの好みやシュチュエーションで使い分けを行っています。
色は当社ではイエローに揃えてますがメーカー、ラフトカンパニーによりそれぞれ特色を
出すため複数の色が取り揃えられています。
アウターチューブとスオートやフロアが色違いとゆうボートも普通にあります。
カラフルなボートが水面に浮かんでるとホント、キレイです!
素材での正式な呼び名は軟質塩ビ系はターポリン、ゴム系はCMSと呼ばれています。
いずれも基材と言ってクロス状の繊維を挟み込んでおり高い強度があります。
ゴム系ではデュポンのハイパロンが有名な素材だったんですが現在は作られて
いません。代わりに日本のアキレスなどがCMSとして販売しています。
色でゆうとターポリンは多数のシートメーカーがあり、バックや変わったところでは
看板などにも使用するので多くの色があります。
CMSはあまり多くは作られていないので色もターポリンに比べると少なめです。
身近な使い道は漁師さん用のカッパや業務用の前掛けなどがあります。
ちなみに海で使用する救難用ボートなどにはCMSのほうが耐久性によるメリットが大きく
使用の例も多いいです。塩水に対する耐久度はCMSの方が優れていると言われています。
ラフトボートの素材としてはCMSの方が耐久性に優れておりその点では向いていますが
ゴム系だけあって素材自体に収縮性があり剛性が足りなく感じることもあり
ターポリン素材のボートを好むガイドも多いです。
この辺は好みで別れるところです。
どちらの素材でもラフトボートとして販売されているものは十分な耐久性、剛性が
確保されていますので通常、岩にヒットしたくらいでは破けたりしません。
が川にある鉄材や鋭く尖った岩などにあたり破れてしまうこともごく稀にあります。
又、長年使っていると経年劣化でボートを持つハンドルや椅子となるスオートなども
傷んできます。
その場合はリペアと言ってボートを補修することもガイドの重要な仕事のひとつです。
シーズンが終わって来るとボートや装備品のリペアで忙しくなってきます。
桂川は岩盤だらけの川ですので年に1艇位は大きく破れることがありますし
経年劣化で痛んでいるボートもありますので大分、リペアの腕は鍛えられました。
ボートはその形状と素材の剛性で性能に違いがあります。
川下りでの性能だけでなくメンテナンス性、やパーツの入手のしやすさなども
選ぶボートは変わります。
川下りの際も河川の特徴や水量によっても求められる性能が違うので使う河川、状況により
合うボートは変わってきます。
場合によってはカスタムして自分達の使い方に合わせたボートにすることもあります。
FACでは使用するボート、ギア類の正しい知識を身に着けメンテナンスをして、より、使いやすく
安全になり、より楽しいツアーを余裕を持って開催できることを目標にしています。
現在、イロイロはメーカーのボートが様々な河川で使われていますので他の川など行くと
ちょっと試し乗りしみたいな~などホント、誘惑されます。新しモノ好きです。
FACラフティングに参加した時、補修の後を見つけたらココってリペアしたんですか~?
てきいて見てください。
担当ガイドがリペアをしてたら面白い話(苦労話)を聞かせてくれるくれるかも?
以上、FACのラフトボートのご紹介でした。